全国規模で対応している大手だからこその
実績と信頼性!

水道修理業者のおすすめ3社はココ!
蛇口の水漏れやトイレの詰まり、床の浸水など、緊急事態に即時出張してくれる優良修理業者をピックアップしました。水まわりのトラブルでお困りの方はぜひご覧ください。
TROUBLE水のトラブルでお困りですか?

通常の修理では複数の業者を見比べて冷静に判断できますが、「水漏れやトイレ・配管の詰まり」のような緊急事態では、何社も比較している余裕はないでしょう。
ましてや、夜間や休日だと対応してくれる業者を探すのも一苦労です。
なかには依頼者が困っているのをいいことに、過剰な修理代を請求する「ぼったくり」のような事例も少なくありません。
「ホームページでは●●●●円と書いてあったのに、実際は数万円の請求となった!」
「今すぐ行くと言いながら、何時間も待たされた!」
「作業直後に再度水漏れが発生し、結局二度手間になった!」
など、緊急事態に付け込んだ悪徳業者に当たらないためにも、実績とノウハウを持った水道業者を選びましょう。
近年増加している悪徳業者に注意
昨今では、トイレなどの水廻り修理に関するトラブルが増加傾向にあります。
2020年10月には、50代の女性が約65万円もの高額な修理代を騙し取られるという許しがたい事例が発生しました。
参考記事:読売新聞オンライン-7万円の工事が「65万円」、水回り修理で高額請求トラブル相次ぐ
このトラブルについては、消費者庁からも注意喚起がなされています。
水道修理サービスは原則としてクーリングオフが認められており、8日以内であれば無条件で契約をなかったことにできます。
例えば、ホームページにある金額とあまりにかけ離れた高額請求をされた場合だと、クーリングオフの対象になる可能性が高いです。
一人で抱え込まずに、まずは消費者ホットラインへとご相談ください。
COMPARE大手水道修理業者10社を徹底比較!

ここで紹介する10社は「全国規模で365日・最短20~30分駆けつけ」のオペレーションを行っている水道修理業界大手です。
夜間・休日の出張はもちろんのこと、事前説明をしっかり行った後、適正価格での修理を約束しています。
また、1日数十件もの水道トラブルを解決しているので、特殊な機器や旧型の設備でもスムーズに対応できるノウハウを持っています。
「とにかく急いでいるが、どの業者に依頼すればいいのかわからない」という方は、当サイト推奨業者の中から選んでおけば間違いありません。
| 業者名 | 到着時間 | 料金(税込) | 営業時間 | 土日祝対応 | 対応エリア | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
 水の救急隊 水の救急隊 |
最短15分 | 5,500円~+作業工賃+部品代 | 0:00~24:00 | ◎ | 全国 |
|
 クラシアン クラシアン |
最短30分 | 8,800円 | 0:00~24:00 | ◎ | 全国 |
|
 住まいる水道 住まいる水道 |
不明 | 5,500円 | 0:00~24:00 | ◎ | 全国 |
|
 水道救急センター 水道救急センター |
最短30分 | 5,500円+作業費 | 0:00~24:00 | ◎ | 関東/関西/東北/東海/北陸 |
|
 富士水道センター 富士水道センター |
最短10分 | 3,300円~ | 0:00~24:00 | ◎ | 7都県 |
|
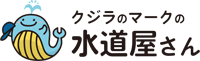 クジラのマークの水道屋さん クジラのマークの水道屋さん |
最短15分 | 3,000円~ | 0:00~24:00 | ◎ | 6府県 |
|
 水110番 水110番 |
30分 | 8,800円~ | 0:00~24:00 | ◎ | 全国 |
|
 街角水道工事相談所 街角水道工事相談所 |
30分 | 8,800円~ | 24時間 | ◎ | 全国 |
|
 クリーンライフ クリーンライフ |
15~60分 | 3,300円~ | 0:00~24:00 | ◎ | 全国 |
|
 水の救急サポートセンター 水の救急サポートセンター |
最短20分 | 4,400円+作業費 | 8:00~23:00 | ◎ | 全国 |
|
BEST3大手水道修理業者ベスト3をご紹介
当サイトで紹介する10社をはじめ、水漏れ・水道修理を担う会社は数千、数万と存在します。
ここでは、到着スピード・料金・営業時間に加え、利用者レビューや強みを総合的に比較し、特にお奨めできる3社を掲載しました。

近畿地方を中心に、47都道府県全てを対象に水道修理を行っているのが水の救急隊です。
「夜間こそ即時対応が必要」という信念のもと、最短15分での駆けつけを約束しています。
WEB割引3,000円が用意されていて、基本料金以上にかかる作業が発生した場合に使うことができるようになっています。
修理後に不具合が起きた時に備えて、お客様相談室を設置しているのも評価できるポイントです。
24時間365日対応可能で、アフターサービスにもしっかり力を入れており、初めての方でも利用しやすくなっています。

トイレのトラブルを解決する大手業者の、先駆け的存在がクラシアンです。
他の業者の名前にピンとこなくても、クラシアンだけはわかるという方は多いのではないでしょうか?
47都道府県各地に拠点を持っており、他の水道修理業者への業務委託ではなく、クラシアン独自の研修を受けた社員たちが修理を行うようになっています。
大手のノウハウによって社員が教育されているため、地域ごとの当たり外れが少なく、技術力やサービスの面では他の大手よりも優れているといえるでしょう。
料金設定がしっかりしており、ネームバリューの高さから高額請求に繋がりにくいという強みもあります。

住まいる水道は、全国どこでも年中無休で利用できる水道修理業者です。
業界最安値をモットーとしており、基本料金が全体的に低く設定されているほか、3,000円の割引キャンペーンまで実施されています。
最短駆けつけ時間は20分で、24時間営業を行っているため夜間の対応OKな点も大きな魅力の一つだといえるでしょう。
その他にも、見積もりや出張にかかる費用は一切発生せず、修理作業を行ったあとの補償にも力を入れています。
MERITなぜ大手の業者がいいの?

水道修理と一口に言っても、街の水道屋さんから上で紹介したような大手の業者さんまで様々です。
しかし、あえて有名どころをお奨めするのには理由があります。
それは「安定した料金」と「誠実性」です。
まず、料金は全国規模で基準が設けられているため、著しく相場から外れた修理代を請求されることはありません。
そして、誠実性に関しても大手の看板を背負っているが故に、不誠実な態度や不適切な工事を行えば、大元の社名を汚すことになります。
昨今は、一個人のインターネットへの投稿が思わぬ拡散を招き、会社存続自体が危うくなるケースも珍しくありません。
例えば、定食チェーン「大戸屋」の従業員がSNSに投稿した不適切動画。
大戸屋はこの件に関わった従業員を解雇、さらに、全国350店舗すべてを休業し、教育や研修の再徹底を行わねばならない事態となりました。
これをきっかけに街中の人々の信頼を失い、2020年にはコロワイドに買収され、そこでも黒字化に四苦八苦している状態です。
水道修理でも同じことがいえます。
小さなトラブルでも、悪意のある過失やぼったくりといえる請求があれば、ネット社会の現代では瞬く間に拡散される可能性があります。
会社規模が大きければ大きいほど顧客トラブルが招く代償は大きく、一つ一つの対応に最善の注意を払っているのです。
MARKET PRICE水漏れ・つまり修理の料金相場

水漏れの場合
水漏れの原因となる部品にもよりますが、蛇口周りであればゴム製のパッキンが劣化し、水漏れを起こしていることが多くあります。
もともと消耗品であるパッキン交換は難易度も高くないので、作業費は3,000~5,000円、部品代も1,000円以下で収まることがほとんどです。
出張作業の場合、別途出張費が加わるか、全てコミコミで8,000~10,000円程度となるのが一般的です。
水漏れでもタチが悪いのは、配管の劣化や蛇口その物の破損です。
露出している蛇口や配管であれば、同型のパイプや部材を手配して組み替えるので、10,000~30,000円の予算で十分収まるでしょう。
壁や床に隠れている配管が水漏れを起こしている場合は、更に大規模な作業が必要です。
一旦内装を剥がして内部の配管を修復or交換するのですが、一度壁・床を破壊するので、費用だけでなく、仕上がりを十分に確認して、納得のいく工事をしてもらうようにしましょう。

トイレつまりの場合
トイレットペーパーの流しすぎや異物混入などは、業務用の圧送ポンプを使用し押し流します。
この作業で済めば、便器を取り外したり、配管を弄ることも無いので、業者の提示している最低価格(8,000~10,000円程度)で収まります。
ですが、異物のつまった場所が悪かったり、流しきれない異物の場合は、便器を取り外し配管を分解する必要があります。
その場合は、分解の度合にもよりますが、10,000~20,000円程度の費用が掛かってきます。
CONTENTS仕組みやトラブルの原因、DIY修理などを解説
当サイトでは「トイレ」「蛇口」「排水管」「エアコン」「給湯器」それぞれについて、次のような内容を詳しく解説しております。
- 種類や仕組み
- トラブルの原因
- 修理費用の相場
- DIY修理
- トラブル予防法
水回りのトラブルが発生した際、故障したもの(蛇口やトイレなど)の仕組みやトラブルの原因を理解していれば、ご自身で部品や工具を準備して簡単に修理することができるかもしれません。
また、トラブルが起きないように予め対策を講じたり、定期的に部品や本体そのものを買い換えたりすることも非常に大切です。
今まさに水漏れや詰まりで困っている方もそうでない方も、ぜひ一度はご覧になって皆様の生活に役立てていただければと思います。
緊急事態は迷わず専門業者を!
蛇口の水漏れ程度ならそこまで焦る必要はありませんが、明らかな浸水や水道管の破損などで水浸しになるような状況なら、1分でも早く専門業者を呼ぶとよいでしょう。
床下まで浸水してしまうとカビやサビの原因になり、集合住宅の場合はさらに、下層階や隣部屋への二次被害も懸念されます。
修理代よりも遥かに高い代償を背負うことになる前に適切な対処をしましょう。






